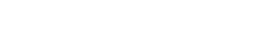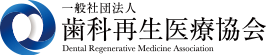新着情報
歯髄再生治療を導入する歯科医院が増加中。 歯科医療を劇的に変えられるのか!?

歯髄再生治療を導入する歯科医院が増加中。
歯科医療を劇的に変えられるのか!?
全国で導入する歯科医院が増加し、症例数も着実に増えてきている歯髄再生治療。
技術提供を担う歯科再生医療協会の中島美砂子氏、国立長寿医療研究センター研究所の庵原耕一郎氏、臨床を行う名古屋RD歯科クリニックの田中宏幸氏に、現状と展望を伺った。
取材・文/長田英一(株式会社クラブメディア) 撮影/スタジオモア

―― まずは、改めてではありますが、歯髄再生治療の意義や目的をお伺いできますでしょうか?
中島 歯髄が歯を守る重要な機能を持っていることは周知の通りですが、歯髄を失うことによる影響は様々です。
反応象牙質や修復象牙質などの第三象牙質が形成されなくなり、免疫調整能や感染防御力も消失してしまうこと。審美性が悪化してしまうこと。知覚という警告信号もなくなるため、細菌が侵入しても気付くことができず、予後不良で根尖性歯周炎になってしまうこともあります。
また、歯髄には物理的機能として硬いものを噛んだときに衝撃を和らげる緩衝作用や、化学的機能として歯に水分や栄養分を与え常に代謝して新しいものに作り変える作用がありますが、歯髄がなくなってしまいますと歯の性状が変化してもろく折れやすくなってしまいます。
庵原 従来の歯科治療は、削って埋めるというもので、完全に元に戻すというよりは人工物で修復するというスタイルでした。
根管治療において、抜髄をして人工物で埋めた場合、20%が根尖性歯周炎になり、そのうちのさらに20~45%が難治性になり最終的には歯を失ってしまうというデータもあります。歯を失ってしまうと、口腔機能が低下しフレイルに陥ったり、認知症や運動機能低下など全身への悪影響を及ぼすことにもなってしまいます。
そんな負のスパイラルを、歯髄を再生することにより遮断することが、歯髄再生治療の目的です。
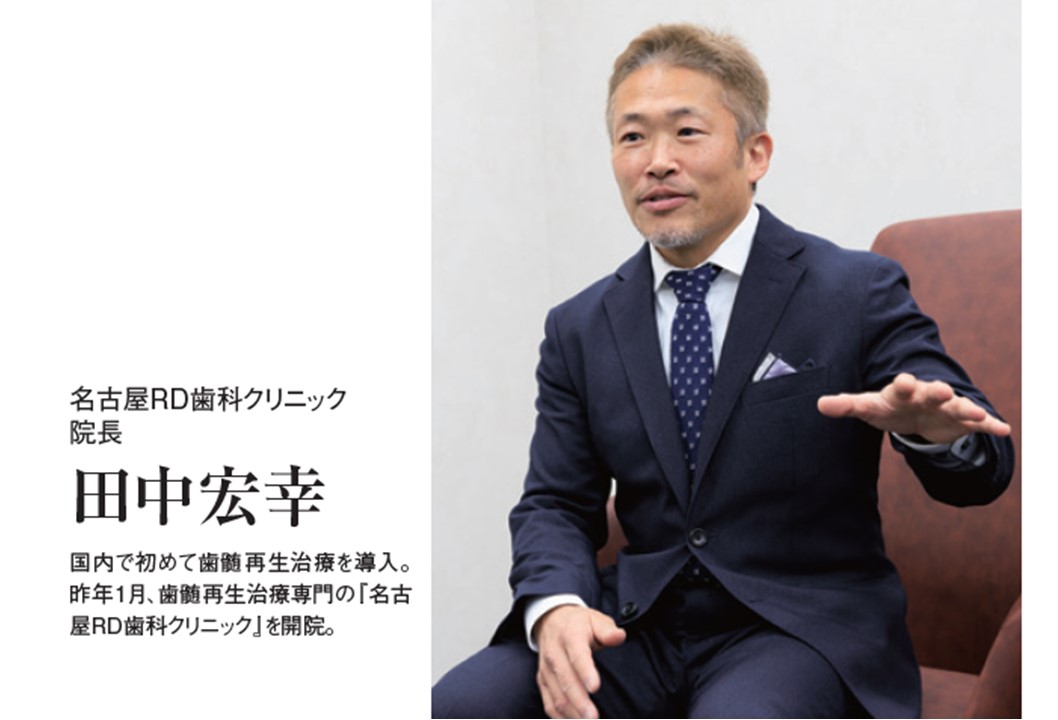
―― 田中先生はどうして歯髄再生治療を導入されたのですか?
田中 保険診療で16年ほど根管治療をやってきたのですが、庵原先生が仰る通り、どうしてもやり直しの治療が多かったわけです。
この負のスパイラルを止めるために、どこかでしっかりと治さなければいけないと思っていたところ、歯髄再生治療を知り、導入を決めました。
―― 実際に導入されてみていかがですか?
田中 親知らずや乳歯からとった歯髄をバンクに送って培養するといったこれまでにないことはありますが、根管内に充填材の代わりに歯髄幹細胞を入れるだけで、治療に関しては特殊な技術も機器も必要ありません。
患者さんとしても、「細胞を移植する」と聞くとすごく大変なことをするのじゃないかと思われる方が多いのですが、動画などを見せて説明すると安心していただけます。
庵原 ただ、細菌の管理レベルは非常に高くしないといけません。
器具の滅菌は当然ですが、クリーンベンチの設置など、普通の歯科医院にはないことも求められます。
田中 移植の際に、『アエラスバイオ社』で培養されて送られてきた歯髄幹細胞を解凍して専用の薬剤を混ぜなければいけないのですが、その際、菌や埃が入らないようにクリーンベンチの中で作業しなければなりません。
そういった作業を行うスタッフの教育も必要になってきます。とは言え、慣れれば問題ない作業ではないかと思います。

―― 歯髄再生治療はどのような方が対象となるのでしょうか?
庵原 歯髄再生治療の対象疾患は、不可逆性歯髄炎や歯髄壊死壊疽、根尖性歯周炎のほか、7歳以上の若齢者の外傷による根未完成失活歯にも対応しています。
―― 実際の臨床現場ではいかがでしょうか?
田中 もちろん、う蝕や外傷などの結果、不可逆性歯髄炎になってしまった方もいらっしゃるのですが、意外に、事故や部活動などの外傷で前歯が失活しまって、元に戻せないですかという相談が多いですね。
一番最初の患者さんも、外傷が原因で前歯にセラミックを入れてらっしゃったのですが、歯髄再生治療を希望して来院されました。一旦神経を取った歯はいつか抜けるんじゃないかと心配だったそうです。
歯髄再生治療の結果、「自分の歯が戻ってきたみたい」と言われたことが印象的でした。
―― それは治療を受けた方しか分からない貴重な意見ですね。
田中 外傷で前歯が失活してしまった方は一定数いらっしゃいますので、ニーズは結構あると思います。特に若齢者の場合、乳歯が残っているケースもありますので、親知らずを抜歯するよりもスムーズです。
また、親御さんがすごく心配して連れてこられますので、何とかしてあげたいという気持ちもあります。
―― 歯髄再生治療を行うにあたり、難しい面はありましたでしょうか?
田中 歯髄幹細胞を移植するには、根管治療を済ませて完全に無菌化しなければいけません。そんなに難しいことを出来るのかと私自身も思っていたのですが、実際やってみると意外に大丈夫ですね。
最初の頃は手間取ることもありましたが、最近では、洗浄を2、3回すればPCRのような厳密な検査でも細菌が検出されなくなってきました。
講習会などでお話しておりますと、根管を無菌化することなんて絶対に無理だと仰られる先生がいますが、そんなことはないというのが実感です。
―― 特別なことをされているわけではないのですか?
田中 技術的に特殊なことはしていないです。ただ、洗浄の際に、一般的には次亜塩素酸ナトリウムやEDTAを使うと思うのですが、それと同時に『アエラスバイオ社』のナノバブル水に抗生剤を混ぜて使用しています。
―― ナノバブル水とはどのようなものでしょう?
中島 ナノバブル水は100~200ナノメートルサイズの空気の泡で、根管壁のスミヤー層を除去出来ると同時に、抗菌剤と併用することにより薬剤の浸透性が高まり、複雑な根管系の奥深くに潜む細菌も除去することが出来ます。
また、バイオフィルムの除去にも効果的です。
庵原 抗生剤だけですと、根管の表面にしか入っていかないのですが、ナノバブル水に混ぜると象牙質の結構奥まで入っていくということは実験で証明されています。
中島 解剖学的にも根管系は非常に複雑で、ただ抗生剤を塗っただけでは効かないこともありますが、ナノバブル水を混ぜると側枝にも入っていきますし、逆に洗い流すことも出来ます。
薬が生体の中に残ってしまうと、幹細胞が影響を受けてしまって良い効果が得られないケースもありますから。
庵原 お話している通り、無菌化する治療法も大切ですが、一方で無菌であるということを検査する方法も重要だと考えています。
今のところ、根管内であれば菌の状態を調べられますが、根尖孔外になってしまうと検査自体が難しくなってしまいますので、検査法自体の確立や精度の向上を目指していかないといけません。
―― 田中先生は、1月に『名古屋RD歯科クリニック』を開業されたそうですが。
田中 元々、名古屋市から車で40分くらいかかる長久手市でクリニックを開業しておりましたが、この歯髄再生治療をやるようになってから、遠方からの患者さんが多くなりまして、通いやすさを考慮して名古屋駅近くに開業しました。
―― 歯髄再生治療専門でやっていらっしゃるのですか?
田中 患者さんの症例に応じて何でもやりますという感じなのですが、現状来られる患者さんが歯髄再生治療をご希望される方ばかりですので、自然とそうなっている感じです。
ただ、歯髄再生治療に付随して、補綴や矯正治療なども必ず出てきますので、経営的にもメリットはあると思います。

―― 田中先生のところのように、歯髄再生治療を導入されているクリニックは全国でどれぐらいあるのでしょうか?
中島 現在、歯髄再生治療を導入されているクリニックが全国で13施設あります。
また、歯髄再生治療を提供するには、技術講習やライセンス取得、特定認定再生医療等委員会や厚生労働省による審査などの流れがあるのですが、この過程にあるクリニックが19施設ございます。
『歯科再生医療協会』としても、各申請に関して歯科医院さんがスムーズに行えるようにサポートさせていただいております。
―― 昨年末、朝日大学との産学連携も発表されました。
庵原 歯髄再生治療の適用拡大を目指していくためには、様々な分野の先生のご意見やご協力が必要になってきます。
歯内治療はもちろん、補綴やインプラント、微生物学、小児歯科もそうです。そういった中で、朝日大学との産学連携は大きな一歩だと考えています。
中島 大学は教育機関でもありますので、将来を担う学生さんたちが早いうちに再生医療に興味を持っていただくことで普及に繋がることも期待しています。
―― 最後に、今後の展望をお聞かせ下さい。
田中 一つひとつ症例を積み重ねていけば、歯髄再生治療の認知や理解も高まってくると思います。まだ、「本当に再生できるの?」という話をされる先生方もいらっしゃいますので、実際に症例数を増やしていくことで証明出来ればと考えています。
庵原 近い将来、被蓋象牙質形成技術や根尖孔外のバイオフィルム除去技術などの実用化により、難治性根尖性歯周炎でも確実に成功出来るようになると考えています。さらに、数年以内には自身に不用歯がない場合でも、他家移植により歯髄再生治療が可能となる予定です。これまでの削って埋めるという歯科治療ではない、新たな治療法の確立に向けて研究を進めていきたいと思います。
中島 日本のデンタルIQが上がってきて、歯髄を残す大切さも含め、歯に対する一般の方の意識も高まってきました。この歯髄再生治療には、人生100年時代の健康長寿に貢献出来る画期的な治療法となる可能性が十分あると思っています。
(デンタリズム (2023年3月号)より)